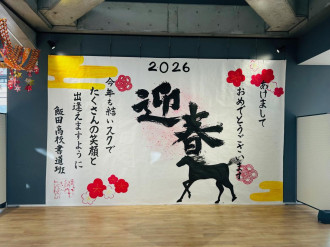飯田華道協会が華道展 会場を新たに7流派51人が作品展示

飯田下伊那地域の7流派で構成する「飯田華道協会」が10月25日・26日、「はにかむべーす内の南信州広域連合 文化芸術活動支援センター」(飯田市上郷)で「第75回華道展」を開催する。
同協会は、中心市街地の約70%が焼失し、3400戸以上が全焼した1947(昭和22)年の大火災「飯田大火」の翌年に行われた「復興感謝祭」に協賛し、2会場で出瓶(しゅっぺい)したのが始まり。当初は吾妻町にあった飯田公民館で開催し、その後は長野県飯田創造館(小伝馬町)でも開かれた。コロナ禍で2年間の休止期間もあったが今年で75回目を数え、同会場での開催は今回が初めてとなる。
現在、協会には遠州流、小原流、花芸安達流、松月遠州流、新生遠州流、松葉古流、龍生派の7流派が所属し、師範を中心に66人が会員登録している。今回はそのうち51人が出瓶(しゅっぺい)し、1人1作品を展示する。
会場では流派ごとではなくランダムに作品を配置し、隣同士が同じ流派となった場合は連作として展示することもある。秋の開催にちなみ、紅葉した葉や、実物(みもの)、花はリンドウやケイトウ、キクなど季節感のある素材を使い、各会員が趣向を凝らす。
普段、地元講師による稽古を重ね、研究会などでは限られた時間に花を生けたり、県内外の講習へ出かけたりして研さんを積んでおり、同展はその成果を発表する機会となる。流派を超えた交流の場としても位置付ける。
同協会会長の渡部裕子さんは「花との出合いは一期一会。同じ種類の花でも枝ぶりや表情が異なり、同じ花や枝は二度とない。初めての方にも気軽に見てもらえれば。これまでの来場者にも、新しい会場でどう変わるのかを感じてほしい」と話す。
会期中は各流派の会員が会場に常駐し、来場者の質問に応じる。渡部さんは「流派の『型』を習得することで、型を応用し生け花を知らなかったときよりきれいに生けられる。興味を持った方は、ぜひ声をかけてほしい」と呼びかける。
開催時間は、25日=10時~17時、26日=10時~16時。入場無料。