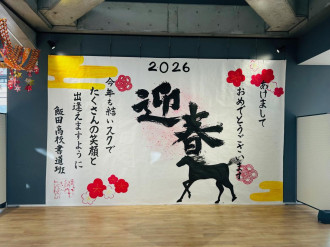飯田市美術博物館・蜂谷充志新館長に「アート」について聞く
4月1日に就任した飯田市美術博物館の蜂谷充志(はちやみつし)館長に話を聞いた。
蜂谷さんは常葉大学(静岡県)造形学部造形学科アート表現領域の教授を務める。インスタレーション、現代アートの分野で作品を制作、発表を重ねる。飯田市出身。
飯田線(当時の国鉄)から上(里山側)には、田んぼとか野原とか果樹園が広がり、恐らく小学校の頃までの記憶が結構強烈です。小学6年から中学へ上がる頃に家の前に中央自動車道が通り、すごく風景が変わった記憶はあります。
進学のため飯田を離れたのですが、情報の差というものを大きく感じました。卑屈になるとかそういうことではなくて、知らないことがいっぱいあるんだなって。背伸びしながらでも吸収していかないと、周りの仲間との情報と経験の差は埋まらないなとも感じました。
アート表現、いわゆる自己表現を研究しています。自分の作家活動がベースになり、その作家活動を元に、学生たちに現場のことを教えたり、そこの現場に近づくように指導したり…。
実践することと、それを裏付ける理論が並行しているということを伝えています。実践は、自分の思い描いたことを具体的に目の前に表す実技で、とても高度な技術力や技術習得です。その技術だけで上手で終わってしまったら、作品として僕の中では面白くないなというのがあって、それを裏付けていく個人の背景というものがとても大事。そこで、理論科目で学んだり、美術の歴史を学んだり…。今の時代に、自分は何ができるかというのを併せて考えないと、いい作品にはならないと思いますね。
小学校での成功体験が、どこかで根っこにあるのかなとは思っています。小学生のときに友達の顔を描くときに、皆は真正面から描いていましたが、僕は真横から見た友達を描いて褒められ、展示会で展示してもらえたことが心に残っています。
父親が割と一部変わった趣味の持ち主で、骨董(こっとう)を集めて、刀剣や煙管(きせる)、棗(なつめ)、七宝焼のつぼとかいろいろなものがありました。国内外の美術全集もそろっていて、勝手に気軽に触っていたと思います。今考えると貴重な体験で、工芸品や歴史の品々、誰かが何かの意思を持って作ったものですよね。好奇心で眺めて触っていました。
「目の前にないものは記憶からなくなるかもしれない」…私の中にずっとあるテーマです。ものは必ず朽ちます。記憶は脳裏に形を残しますが、消滅もします。作品と出合った記憶によって変化した体験は、すり傷のように心の中に残って、その後に作用する。そんな考え方自体も作品と思っています。
薄いベールの先にあるぼんやりとした光じゃないかな…何かわからないけれど、みんなが薄いベールを自分の力でペラペラっとこうめくりながら、その光を求めてアートって何?って…。確固たる一つの答えではなく、でもみんなが何かなって興味を示しながら、一枚一枚ベールをこうかなって(めくっていき)、答えを見つけようと思ってもつかめない。

大きな文化というものは観覧車みたいなもので、その地域のシンボリックにあって、いつもゆっくり回っていて乗りたいときには乗りに行けるし、そこは安心感があり何かが行われている。いろいろなことにいつでも参加できる。
観覧車の骨組みというのは、やっぱり歴史だと思う。その歴史を積み重ねるごとに堅固になって、その堅固な力強さの中でゆっくり物事が回っていく、それが文化じゃないかな。ここは自然科学もあるし美術もあるし、文化の拠点だし飯田のインストっていうか研究機関としても誇りを持っていい。そこに興味を持った人がいつでも足を踏み入れてくれる、関わってくれるというのはすごくいいのかなと思っています。
インタビューの内容はコミュニティーラジオ局「飯田エフエム放送」の番組「ビビビビーナス」(金曜13時~13時30分)の中で6月中に放送。