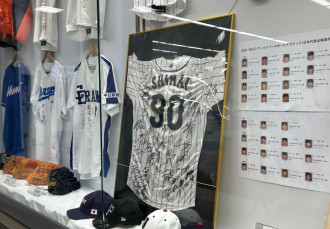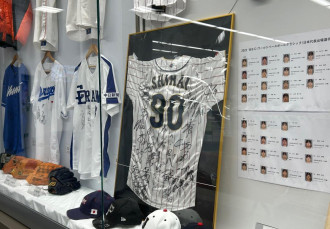阿南町の「早稲田人形浄瑠璃」 早稲田神社で恒例の奉納公演

国の選択無形民俗文化財指定50周年を迎えた「早稲田人形浄瑠璃」の奉納人形芝居が8月24日、早稲田神社(阿南町西條)の舞台で行われた。
早稲田人形は、阿南町西條早稲田地区の伝統芸能で、8月の第4日曜日に同神社の本祭で奉納上演される。江戸時代から続くとされ、舞台での上演前に拝殿で神事が執り行われ、白装束の3人が「三番叟(さんばそう)」を上演するのが特徴。
人形芝居は、淡路や文楽と同じ1体の人形を3人で操る「三人遣い」で、太夫(たゆう)の語る声と三味線の伴奏により、せりふや節などに合わせて動かしていく。
当日は、同人形保存会員約20人が、五穀豊穣などを願う「三番叟」のほかに、近松半二(ちかまつ はんじ)や三好松洛(みよし しょうらく)らによる合作の時代物で、戦国時代の武将、上杉謙信と武田信玄の争いを背景に、謙信の娘「八重垣姫(やえがきひめ)」が、信玄の息子「勝頼」に寄せる熱い思いを描いた「本朝二十四孝(ほんちょうにじゅうしこう) 四段目 十種香(じゅしゅこう)の段」を上演。客席から、おひねりが飛ぶ場面も見られた。
公演には地区内外から約30人が来場。松川町から2年程ほど前に同町に引っ越してきたという90代の女性は、友人と一緒に観劇。「素晴らしい芝居を見せてもらった。歴史ある文化を、この先も残していってほしい」と期待を込めたる。
演者として参加した阿南第一中3年の熊谷泰珠さんは「人形芝居を始めて1カ月くらいだったが、練習通りできた。人形操作は難しいが楽しい。今後も続けていきたい」と振り返る。